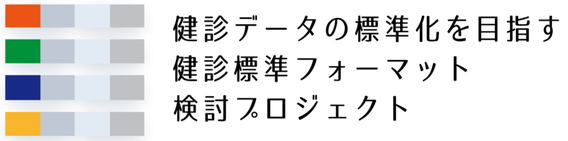お知らせ ===
HASTOS等利用申込書ダウンロードはこちら NEW!
HASTOSサービス利用申込書(健診機関) 資料1
HASTOSサービス利用申込書(実施主体代行機関) 資料2
POST.exソフトウェア使用許諾申込書 資料3
POST.ex ver4保守継続申込書(修正) 資料4
近況 =====
2025.6.1 NEW!
2025年4月より一般社団法人により商用版HASTOSのサービスが開始されました。
6月1日現在の登録施設数を公表します。施設名はPOST.ex配布施設一覧を参照ください。
健診標準フォーマットは健診機関が710施設、その他団体(企業、大学、代行機関)が15団体となっており、725施設団体が利用しております。
商用版HASTOSを契約している施設は182施設であり、クラウドサーバー上で健診標準フォーマットへの変換サービスが利用されています。
2025.2.22 健診標準フォーマット(KMAT ver5.0、2000項目)を公開します。
HASTOSを経由して納品される健診結果データにはすでに採用されています。
ver5.0では特殊健診項目、地域がん検診、HL7-XML形式対応項目等の見直しを行いました。
なお、2025年度中にこれまで採用してきた1500項目から2000項目に完全移行します。
2025年度も継続してVer4.xを利用される場合にはPOST.ex.ver4.保守継続申込書(資料4)を必ずご提出ください。

2025.2.15 内閣府・厚生労働省の補助を受けて一般社団法人 日本医学健康管理推進機構が設立されました。
日本医学健康管理評価協議会が推奨する健診標準フォーマットの仕様で健診機関が事業主や医療保険者に標準化された健診結果データを納品できる仕組み(HASTOS)を社会実装し4月からサービスを開始します。 HASTOSに関する情報はこちら → https://hastos.jp/
2025.2.4、6、7 一般社団法日本医学健康管理推進機構(設立準備室)がHASTOSのサービス開始について説明会を行いました。本説明会のビデオ及び資料を公開いたします。
(説明会投影資料)
0.【冒頭説明】本日のご説明に関する留意点について(資料0)
1.健診機関向け説明資料(資料1)
2.健診実施主体・代行機関向け説明資料(資料2)
3.(参考)HASTOS操作説明資料(資料3)
4.HASTOS説明会当日のQ&A(資料4)
(各種申込書)
word文書に必要事項を記載して jimukyoku@hastos.jp 宛にメール添付でお送りください。すでに申込をしている施設は再利用させていただきます。
1.HASTOSサービス利用申込書・健診機関(資料1)
2.HASTOSサービス利用申込書・実施主体代行機関(資料2)
3.POST.exソフトウェア使用許諾申込書(資料3)
4.POST.ex.v4保守継続申込書(資料4)
(当日の説明内容)
2025.1.30 一般社団法日本医学健康管理推進機構(設立準備室)が以下の日程でHASTOSについて説明会を行います。健診機関様、健診実施主体様には個別にWeb会議のご案内を個別にお送りいたしております。本説明会のビデオ及び資料は来週中に公開いたします。
(ご案内が漏れておりましたら「お問い合わせ」からご連絡ください)
1.説明会日時
(健診機関向け)
1回目 : 2025/2/4(火) 16:00-17:00
2回目 : 2025/2/6(木) 16:00-17:00
(健診実施主体向け)
1回 2025/2/7(金) 16:00-17:00
2.開催方法
ZOOMによるオンラインミーティング 以上です。
2024.11.6 日本医学健康管理評価協議会がハイブリッド形式で行われ、会議の中でHASTOSを運営する団体として、一般社団法日本医学健康管理推進機構(設立準備室)が登記されたことが報告され、活動が開始された。
2024.10.1 これまでは一部の施設限定でしたが、 HASTOSの実運用が始まりました。サービスはPOST.exオンラインのみです。
(HASTOS利用申し込みをいただいた施設から順次利用可能です。準備が整ったらメールで実務担当者に連絡いたします。サービス申込書)
2024.8.7 HASTOSの利用申し込みを開始しました。なお、経産省および厚労省のガイドラインの関係性について公表します。
1.HASTOSと経産省ガイドラインとの関係資料差し替え
2.HASTOSと厚労省ガイドラインとの関係資料差し替え
2024.8.5 健診標準フォーマット(KMAT ver4.1)を公開しました。
(ver4,0 → ver4.1に修正しました)
1)HASTOS上のPOST.exオンラインで変換されることでver4.0となります。
2)項目数は2000項目で、1500項目まではver3.3と項目は同じです。
3)20250401より健診実施主体はKMATライセンス費用が必要となります。
2024.7.12 日本医療健康管理評価協議会への説明に続き、健診機関の担当者向けにHASTOSの利用方法を含めて説明会を開催した。説明会の主旨は、健診標準フォーマット変換ツール(POST.ex)の利用者が急激に増加することが予想されるためにその利用方法をダウンロード型からサーバー型に変更することです。この説明会は7/17,7/19にも繰り返し行われます。
2023.9.26 HASTOSのプレサービス開始説明会で使用した資料を公開します。
健診機関向けに2023/9/15,/19,健診実施主体向けに2023/9/21,/22 の計4回説明会を実施しました。健診機関向けの説明会では15日に160施設,19日に130施設,21日に40団体,22日に30団体が参加していただきました。説明会資料
10月にも追加で行う予定です。参加希望者はoffice@postex.jpにお申し込みください。
2023.9.1-2 HASTOSのプレサービスを開始します
第64回日本人間ドック学会学術大会(高崎)でブース展示を行い、HASTOSのプレサービス開始の案内を行いました。説明会は以下のQRコードからお申し込みください。
または、直接接続してください。https://forms.gle/tSRa8mtCTUrX3P6v8
なお、上記で都合がつかない施設向けに、10月,11月にも計画しています。別途連絡させていただきます。


2023.7.12-14
モダンホスピタルショー2023東京ビッグサイトでブース展示を行いました。


2023.7.1
健診標準フォーマット ver3.3を公開しました。
1)特定健診第4期対応を追加しました。
2)特殊健診項目の見直しを行いました。
3)新規項目以外はver3.2の項目の名称変更で、登録内容に変更はありません。
但し、これまで利用がなかった項目については内容の見直しを行っています。
2023.6.28
日本医学健康管理評価協議会 総会・WG 合同会議 がWeb形式で開催されました。
討議内容
1)厚生労働省からの調査依頼、2)健診データ標準化担当WG委員の追加、
3)HASTOS運用実証実験結果について、4)HASTOS本格運用の実施体制について
2023.6.28
HASTOS実証実験結果を公表しました。
2023.3.31
40歳未満の事業者健診の実施にあたり、HASTOSが通知に明記されました。
保発0 3 3 1 第5 号 (4ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001081428.pdf
2023.2.28 - 3.7
HASTOSの運用に係る実証実験について参加予定の健診機関に向けて
Web会議で説明会が4回繰り返して行われました。
HASTOSについて

2022.12.26
日本医学健康管理評価協議会 総会・WG合同会議が行われました。
HASTOS運用に係る実証実験について協議会の皆様に協力を依頼しました。
健診データ標準化担当が協議されました。 資料
2022.9.2
第63回日本人間ドック学会学術大会 幕張メッセ国際会議場で「HASTOS🄬」の紹介を行いました。

2021.12.5
健診標準フォーマットver3.2の説明会が開催されました。
説明会資料は活動状況に掲載しました。
2021.11.10
日本医学健康管理評価協議会WGが開催されました。
2021.11.04
健診標準フォーマットver3.2の健診実施主体側への説明会が開催されました。
2021.9.24
第62回日本人間ドック学会特別企画2で健診標準フォーマットが取り上げられました。
健診標準フォーマットについて
● 健診標準フォーマットとは
健診関係10団体(右に表示)で構成する日本医学健康管理評価協議会が総意で推進している電子的標準様式である。健診標準フォーマットを基にした生涯健康管理基盤(プラットホーム)を構築することで幼少期から老年期に至る健診(検診)データの一元管理を実現できる。
● 健診標準フォーマットの特徴
•全ての健診への対応が可能である。
•1受診者1履歴1レコードで表現される。
•健診標準フォーマットへの変換は統一された専用の変換ツールを利用する。
•健診標準フォーマットではコードを使用せず、名称・用語が登録される。
(一部、特定健診や特殊健診では国内法のコードが用いられる)
•画像所見などは類義語集により用語の標準化を目指す。標準化WGを医師により構成している。
•判定は機能別判定、臓器別判定の両方を管理するが、判定方法には健診機関個々に特徴があるので、
変換ツールでは自動判定処理を行わない。なお、判定の用語は標準化する。
•検査方法など由来情報は検査結果データとは別に管理し、分析用データベースを構築する際には統合し、高精度な分析を可能にする。
● 健診標準フォーマット変換ツールの特徴
•健診標準フォーマット変換ツールは健診機関に対して配布される。
•健診事業者の作成した個別CSVファイルを健診標準フォーマットに変換する。
•用語などは自動的に標準用語に変換できるので、標準用語の利用を健診機関には強要しない。
•変換ツールはCSVファイル対応(POST.ex)とXMLファイル対応(POST.ex7)の2種類がある。
•特定健診の「検査実施フラグ」や「労基署用有所見フラグ」が自動設定される。
•変換ツールは日医総研が健診機関に無償配布する、健診機関別に変換表が必要となるので、対応表
設定費用だけは有償(税抜5万円)となる。
● 健診標準フォーマットを利用するメリット
•健診機関にとっても健診委託者(代行機関含む)にとっても、データ変換作業の効率化が図れる。 同時にシステム間の相互運用性が向上する。
•用語が標準化されるので所見などの集計が容易になる。
•データ変換される回数が激減するので変換ミスがなくなり、高品質なデータベースが構築できる。
健診標準フォーマット運用の概要図

健診データの健診標準フォーマットへの変換手順の概要
健診機関における健診データの健診標準フォーマットヘの変換作業は健診機関所属のシステム担当者と日医総研(健診標準フォーマット管理事務局)が共同で作業を行う。
健診機関からは以下の①利用機関登録票、②由来情報調査票、③変換元CSVファイル、④健診結果個人報告書、⑤判定コード表・画像部位所見コード表等を揃えて事務局に送付する。
1)①利用機関登録票は
変換ツールを利用している健診機関を登録管理にするために必要となります。
2)②由来情報調査票(1、2、3)は
健診を実施する際の測定方法等詳細な健診運用情報を調査します。変換テーブルを作成する際に
利用します。年1回の更新処理を行います。
3)健診システムに登録されている健診結果データを抽出するプログラムを特定する。
現在使用している抽出ツールで、一番多く項目を抽出できるツールを利用してください。
NTTDATAのHealth Data bBank用のMd3.0等のCSVファイルであれば結構です。事務局に相談して
ください。(新たな投資は最小限にしたいものです)
4)上記抽出プログラムにより、ヘッダー付きの③変換元CSVファイルを作成する。
・結果項目の出力順番(ヘッダーの並び)は健診機関の個別順で構いません。サンプル数は最低
1,000件程度必要となります。
・判定及び画像所見関係項目の結果値はコードでなくコードの名称に置き換えて提出してください。
・変換元CSVファイルには「健診標準フォーマット」の項目番号1から16項目までは必ず、
ヘッダーに設定してください。健診システムに存在しない項目はnull値を埋めてください。
5)変換表設定の際に利用しますので人間ドックなど項目の多い④健診結果個人報告書の雛形、
⑤判定コード表・画像部位所見コード表をお送りください。